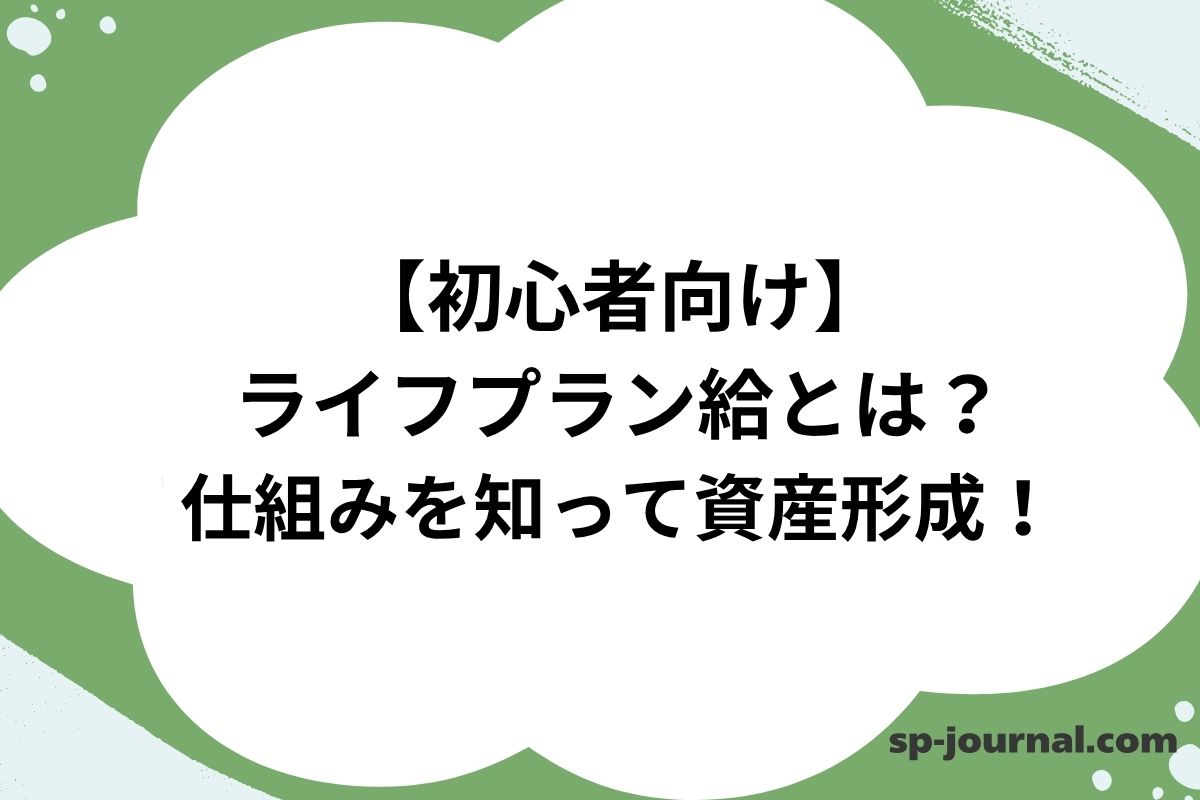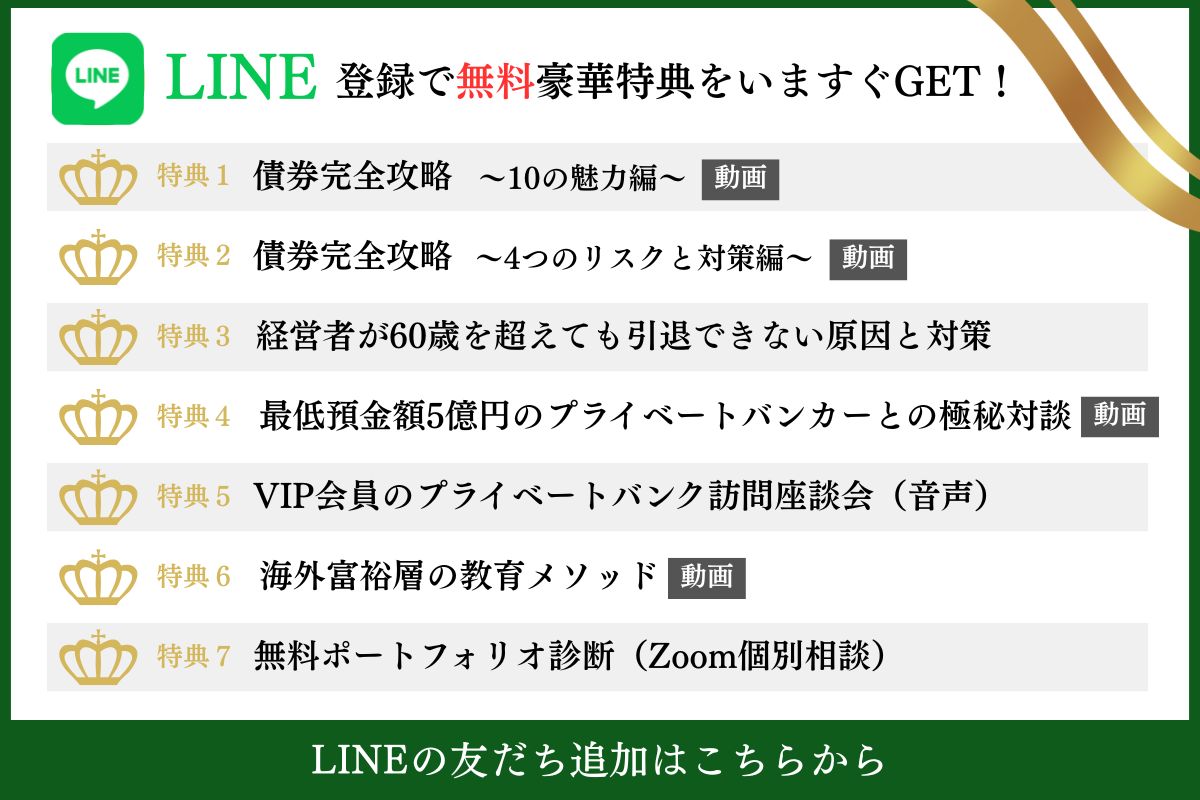「ライフプラン給」という言葉、聞いたことはありますか?勤務先で取り入れられて、よくわからないけれど運用が始まっていた、という方も多いかもしれません。
ライフプラン給については、今でもこんな声が数多く聞かれます。

「ライフプラン給」って聞いたことはあるけど、どんな仕組みなのかしら?



結局のところ、給与やボーナスの手取り額はどうなるの?
ライフプラン給は、どこの企業でも取り入れているものではないので、誰もが聞く言葉ではなく、初めは少しわかりにくいかもしれません。
しかし、ご安心ください。今回は、そんなライフプラン給の基本的な仕組みから、将来にむけての資産形成方法について解説します。ライフプラン給とは何なのか、メリットやデメリットは何か、そして最も知りたい「給与やボーナスがどう変わるのか?」について、わかりやすく、かつ詳細に解説しますよ!
ライフプラン給は、実は将来のために毎月ちょっとずつお金をためておく制度なので、その仕組みさえわかれば、給与明細の内容も理解できますし、手取り額が変動して不安になることもありません。安心してライフプラン給の運用に取り組めますよ!
ライフプラン給を積み立てていく最終的な目的は「将来の資産形成」です。制度への理解を深めて上手に運用していけば、必ず「老後の安心」にもつながります。



この記事で、ライフプラン給のメリット・デメリットをしっかり理解した上で将来の資産形成に役立てられるよう、プライベートバンカーの観点から説明します。



この記事を皮切りに、ぜひあなたも、将来の安心を手に入れてくださいね!



この機会にしっかり学んで、将来に備えます!
ライフプラン給とは何か?
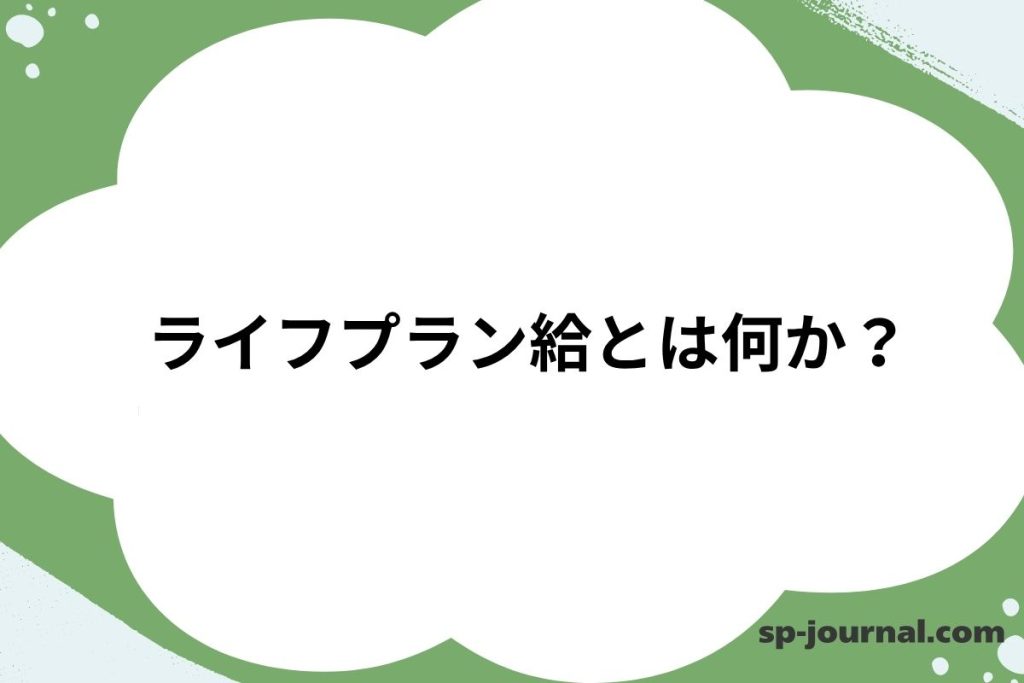
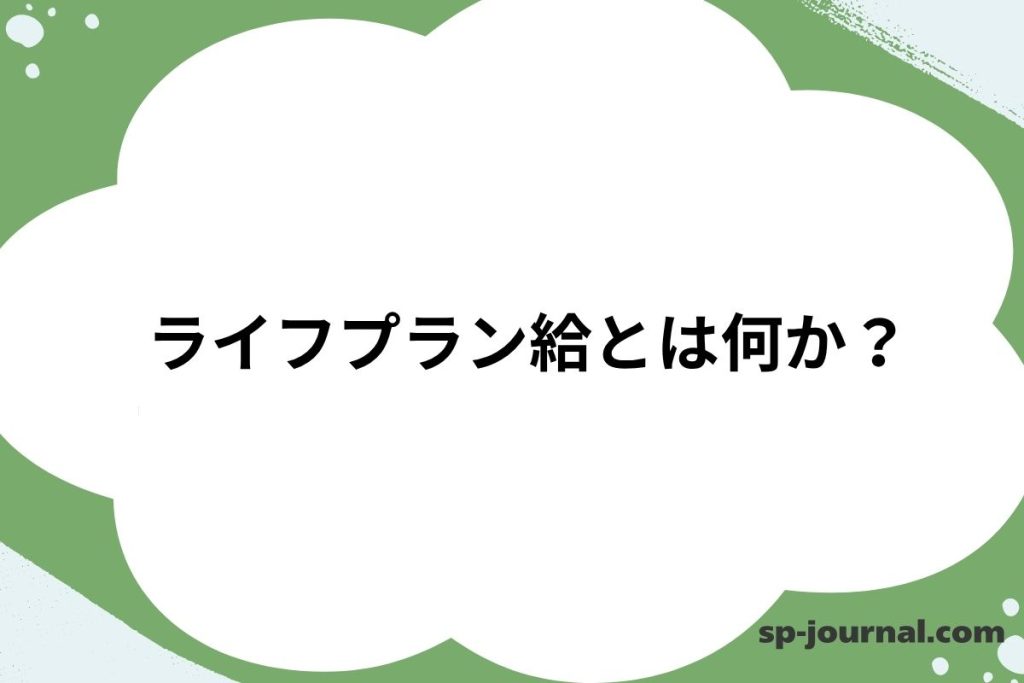
ライフプラン給とは、従業員の将来生活設計や老後の資産形成を支援するために、企業が提供する福利厚生制度のひとつです。給与の一部を確定拠出年金に拠出できるようにすることで、従業員が自らのプランに沿って資産形成できる仕組みになっています。



それでも、まだ少し難しい感じがしてしまいます。



ごく端的に言うと「ライフプラン給」=「資産形成をするための給与」のことです。
もう少し説明すると、給料の一部を年金として積み立てて、退職した時にそのお金を受け取れる仕組みなんです。
ライフプラン給分は節税対策もできるので、結果として生涯で受け取る金額が増えることになります。とてもお得になる制度だと捉えてくださいね。
ライフプラン給の基本概念
さて、それではライフプラン給の基本概念について説明しましょう。



給与の一部を企業年金に拠出するって聞くと、毎月のお給料が減ってしまわないか不安です。
確かに、給与の一部が拠出されるので手取り額が減ります。しかし、その拠出額は非課税なので節税ができるのです。さらに60歳になれば、その積み立て金を受け取れるので、生涯で受け取る金額は増え、長期的に見れば大きなメリットがあると考えてください。



それでもまだ少し不安です。具体的な例を教えてもらえませんか?
もちろんです!例えば、私の知り合いの山田さん(仮名)も最初は給料が減ってしまうのではととても心配していました。
そこで山田さんの給与について、ライフプラン給を拠出した場合と、そうしなかった場合で実際に計算してみました。この制度を使って拠出した給与分は非課税となるため、税金としての支払いが抑えられ、実質的には資産が増えます。山田さんは、それを理解して安心していました。
そして「ライフプラン給としての拠出は、長期的な資産形成につながる」と理解してからは、不安は解消されたようです。退職時には十分な資産を確保できるので、「今では将来が楽しみになりました」と喜んでおられましたよ!



ライフプラン給として給与の一部を拠出するこの制度は、プライベートバンカーとしても、メリットは非常に大きいと感じています。



もちろん、私自身もライフプラン給を活用して資産形成していますよ。将来の不安がひとつ減りました。
給与明細をみると、手取りが減っているように思えて不安を感じてしまう方が多いかもしれません。しかし、実際に運用を始めると、不安は徐々に払しょくされていくはずです。
ライフプラン給の導入背景



ところで、ライフプラン給っていつから、なぜ始まったんですか?



2001年に法律ができて、運用が開始されました。日本版401kとも言われています。
2001年に「確定拠出年金法」という法律ができ、日本ではそこから制度が始まりました。この制度には「公的年金を補い、自助努力によって老後資金を準備する」という意図があります。
(出典:日本M&Aセンターより)
導入の背景には、少子高齢化の進展があります。高齢期の生活が以前とは異なり多様化していることや、社会経済情勢の変化を踏まえ、老後の経済的な安心と安定を、公的年金以外からも得られるように、と始まりました。
公的年金には、国民年金と厚生年金があります。この2つの公的年金に加え、3つ目の年金として私的年金制度がもともと存在しています。将来の経済的安定を自助努力で備えていくため、私的年金制度のひとつとして、新たに国が制度を定めました。それが確定拠出年金です。
この確定拠出年金には、企業型と個人型の2種類があり、さらに企業型も次の3つのタイプに分かれています。
企業拠出型(会社負担型)
会社が掛け金を全額負担します。
上乗せ型(マッチング拠出型)
企業と従業員の両方が掛け金を拠出します。
選択制(給与振替型・選択制DC)
給与の一部を掛け金として拠出するか、そのまま給与として受け取るかを、従業員が選択できます。
※どのタイプも運用は従業員自身が行います。
ライフプラン給とは、この中の3つ目のタイプ「選択制確定拠出年金」で、掛金として拠出される給与のことを指しています。では、このライフプラン給が毎月の給与やボーナスに与える影響について、次で詳しくみていきましょう。
ライフプラン給が給与やボーナスに与える影響
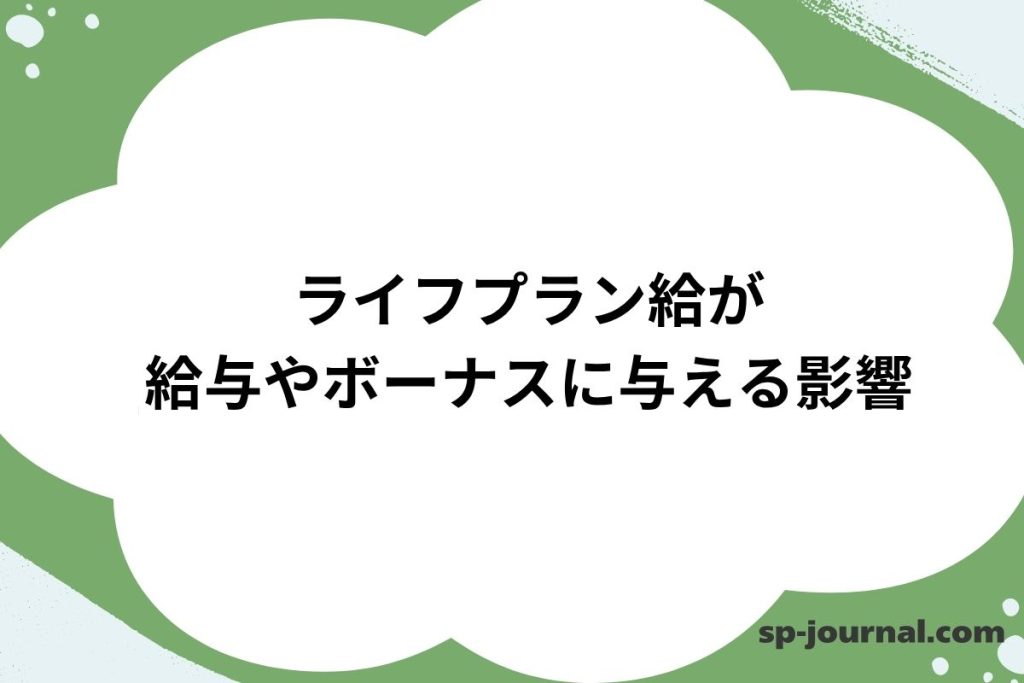
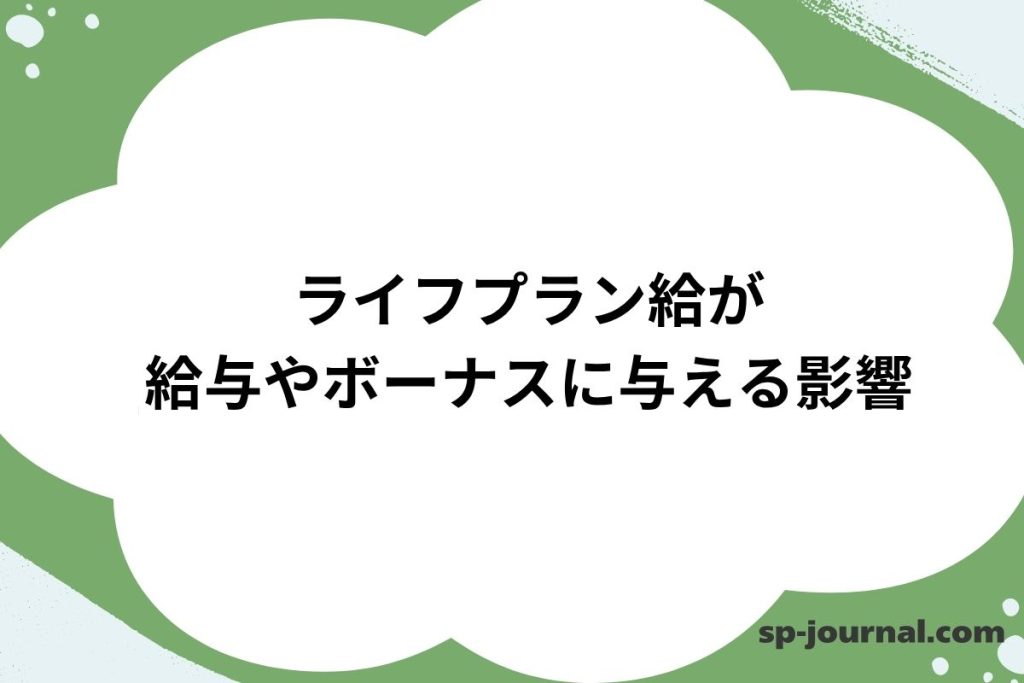
では、ライフプラン給は、毎月の給与やボーナスにどのような影響を与えるのでしょうか。



生涯にもらえる金額として増えるとわかっても、やっぱり手取り額が減ることは不安です。
ライフプラン給は毎月の給与そのものや、ボーナスに影響が出ます。ここでは、その具体的な影響について、基本給、ボーナス、給与明細の項目の3つに分けて、それぞれ詳しく解説していきましょう。
基本給はどうなる?
まずは基本給です。この基本給からライフプラン給が差し引かれるので、手取り額は減少することになります。しかし、ここで重要なのは、ライフプラン給は非課税であるということです。
他の制度では、基本的に各種保険料や税金などが差し引かれた後に拠出します。しかし、ライフプラン給の場合、基本給からライフプラン給を差し引いた金額が課税対象として計算されるので、その分、各種保険料や税金が低く抑えられるのです。
拠出金額分が手取り額からは減りますが、一定額を積み立てつつ、保険料・税金の支払いは少なくてすみます。
ボーナスはどうなる?
ボーナスからも一定割合をライフプラン給として拠出が可能です。これにより、ボーナスの総支給額が変動する場合があります。最初は少し驚くかもしれませんが、こちらも給与と同じで、長期的には資産形成の一環として非常に有効なのです。



それでもやっぱりボーナスが減るのは嫌です。具体的な影響を教えてください。
私のクライアントの山田さんも、ボーナスが減ったことに不満を感じていました。「せっかくのボーナスが減ってしまうなんて」と不満を漏らしていましたが、運用する額が増える=運用益も増える、ということと、実際に運用益が期待以上に成長していたことを知り、その不満はきれいに解消できたようです。
また、基本給と同様に、ボーナスから拠出したライフプラン給は非課税対象ですので、ボーナスから差し引かれる各種保険料や税金は少なくなります。
山田さんは「今は拠出することの方が大事だと感じています。将来が楽しみです。」と現在では積極的に拠出額を増やしています。実際に運用益が増えていくと、将来への安心感も増していきますよ!
給与明細に追加される項目
ライフプラン給は給与の一部を年金として拠出するため、給与明細には新しい項目が追加されます。



ライフプラン給が導入されると、給与明細にどのように表示されるんですか?



実は項目の名称は決まっています。生涯設計手当という名称がライフプラン給に該当します。
ライフプラン給として給与明細に追加される項目は「生涯設計手当」という名称になります。ライフプラン給を導入した企業であれば、どの企業も同じ項目名称です。
他にも追加される項目があります。ライフプラン給は選択型確定拠出年金ですので、ライフプラン給の一部を給与として受け取り、残りは年金に拠出、というプランで運用していくことも可能です。そしてそれぞれに項目名称が決まっています。
《導入前》
総支給額 = 基本給 + 各種手当
《導入後》
総支給額 = 基本給 + 生涯設計手当 + 各種手当
《具体例》
基本給 250,000円 + ライフプラン給 50,000円
給与として支給 10,000円、年金への拠出金 40,000円 だった場合
| [支給] | |
| 基本給 | 250,000 |
| 生涯設計手当 | 50,000 |
| 確定拠出年金掛金 | △40,000 |
または
| [支給] | |
| 基本給 | 250,000 |
| 生涯設計前払金 | 10,000 |
| (空白部分などに) | |
| 確定拠出年金掛金 | 40,000 |
と記載されます。一見すると支給額が減っているように見えてしまい不安になるかもしれません。しかし、総額は変わらないので、明細をしっかり読み込んで理解すると、安心できるはずです。
例えば、私のクライアントの田中さん(仮名)は、初めて給与明細でライフプラン給の項目を見た際に戸惑ってしまい、すぐに私のもとに相談に来られました。
「支給額が減っているのはどうして?」と不安を感じていましたが、給与明細をひとつずつ説明したところ「これは将来の自分への投資なんですね!」と、納得していただきました。その後、田中さんは拠出を続けています。近況を訪ねると、「今では未来への備えができている感じがして、安心して毎日を過ごせています。」と笑顔で話してくださいました。
私自身も、給与明細に新しい項目が追加され、手取りが減ることに少し戸惑いました。しかし、拠出分は非課税なので、その節税効果と長期的な資産形成のメリットを考えると不安は全くなくなりましたよ!



プライベートバンカーとしても、ライフプラン給の運用は、安心・安全に将来の資産形成ができる方法であると、胸を張ってお伝えすることができます!
ライフプラン給を活用するメリットとデメリット
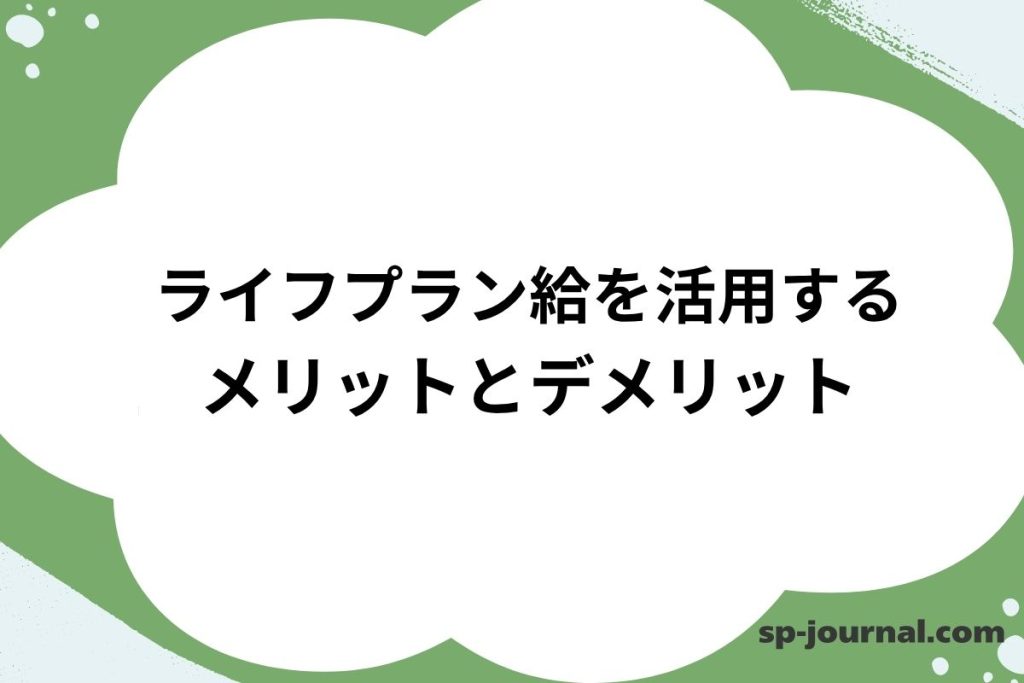
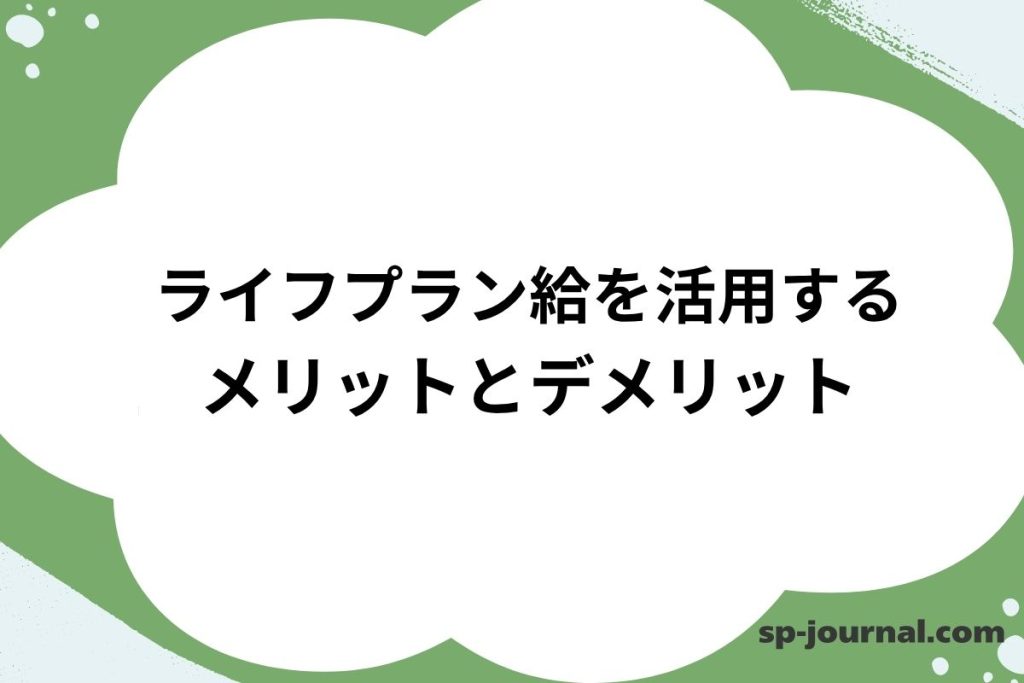
ライフプラン給を活用すると非常に大きなメリットを数多く享受することができますが、当然デメリットも存在しています。メリットとデメリットの両方を理解しないままでは、効果的なライフプラン給の運用は不可能です。このセクションでは、その両方について詳しく解説しましょう。
メリット: 節税効果と将来の資産形成
ライフプラン給のメリットは、大きく一言でまとめてしまうと「将来の資産形成ができる」ことに尽きます。



将来の資産形成といっても、なんだかイメージがわきません。



具体的にどんな良いことがあるんでしょうか?
ライフプラン給を活用すれば、老後資金を計画的に準備できることが1つ目のメリットです。給与からライフプラン給が差し引かれるので、今の手取りが減ることにはなりますが、強制的に貯金している、と考えれば、普段の生活で節約するより、はるかに大きな金額を貯めていくことができます。
2つ目のメリットは、節税効果です。拠出した分は非課税となります。ライフプラン給では、拠出した金額を積み立てて運用するので、運用利益=運用益が発生しますが、なんと、その運用益も非課税なんです。運用がうまくできていないと分かったときは、運用の見直しも可能なので安心ですね。
また、基本給が少なくなる分、社会保険料も引き下げられます。節税と社会保険料の引き下げ分は、最終的には手取り額に反映されますので、これもメリットの1つといえますね!
さらに実は3つ目のメリットがあります。それはポータビリティ制度です。転職時にライフプラン給で積み立てられた年金資産は課税されずに次の企業に移行でき、積み立て期間を継続させることができます。
次の企業がライフプラン給を導入していない場合や、離職した場合でも、他の年金制度へスムーズに移行ができるので、大変便利な制度です。転職の際の手続きはとても煩雑ですが、この制度があることで、安心して資産移動ができます。
他に、もし企業が倒産したとしても、拠出して積み立てた分は保護されるので、資産が失われることはないのが安心です。この安心が、4つ目のメリットとして挙げられます。



運用についても見直しができることも、プライベートバンカーの観点から見ると、大きなメリットの1つなんです。



私自身も毎年の拠出額や運用を見直し、老後に向けてしっかりと資産を形成していますよ。
老後資金の資産形成ができる
拠出した掛金と運用益は、すべて非課税、社会保険料の負担減、運用見直しも可能
ポータビリティ制度があるので、転職時の資産移動がスムーズ
積み立て金は勤務している企業が倒産しても保護される
デメリット: 制度の理解と運用リスク
ライフプラン給にはメリットだけでなく、デメリットも持ち合わせています。ここからは、そのデメリットについて解説していきましょう。



ライフプラン給のデメリットって何ですか?



積み立てなのにデメリットがあるときくと、不安を感じてしまいます。
ライフプラン給における1つ目のデメリットは、給与手取り額が減ってしまうことです。長期的には得をすると理解していても、今すぐお金が必要になる場面もありますから、不安を感じてしまうかもしれません。
そして、2つ目が60歳までは積み立て金を引き出せないことです。ライフプラン給は将来の年金なので、途中で止めることができません。例外的に可能な場合もありますが、条件は非常に厳しいものになっています。
3つ目のデメリットは、運用リスクです。ライフプラン給は運用方法を自分で選ぶ方式になっています。元本保証型のプランを選ぶこともできますが、投資型のプランを選ぶことも可能です。この投資型を選んだ場合、リターンが大きいとしても、元本割れのリスクを負う必要があります。
あるクライアントは、運用リスクを恐れ、最初はライフプラン給を避けていたという事例があります。そのクライアントは「リスクが怖くてどうしても踏み出せない」という漠然とした不安があり、今後の運用について相談に来られました。
そこで、リスク管理の方法や投資先の選定について丁寧に説明すると、徐々に理解してくれて、現在では自ら進んで運用を行うようになりました。
リスク管理や投資先を検討するためには、ライフプラン給の制度そのものをしっかり理解することも必要となってきます。そもそも年金制度自体を理解することは難しいですし、運用についてもさまざまな方法があるので、簡単に理解できるものではありません。4つ目のデメリットは、この制度を理解することへの難しさです。
私自身も運用を始めた際、最初は制度を理解するのに時間がかかり、運用リスクに対しても不安を感じていました。しかし、制度やリスク管理をしっかりと理解し、適切な投資先を選ぶ方法を学んだことで、不安は解消され、メリットの大きさをより期待できるようになったのです。



クライアントに対しては、プライベートバンカーとして、この制度のメリットだけでなくデメリットを正確に伝えることが重要だと感じています。
給与手取り額が減少する
60歳まで引き出せない
運用リスクがある
制度を理解するのが難しい
ライフプラン給は退職金や他の年金制度と何が違う?
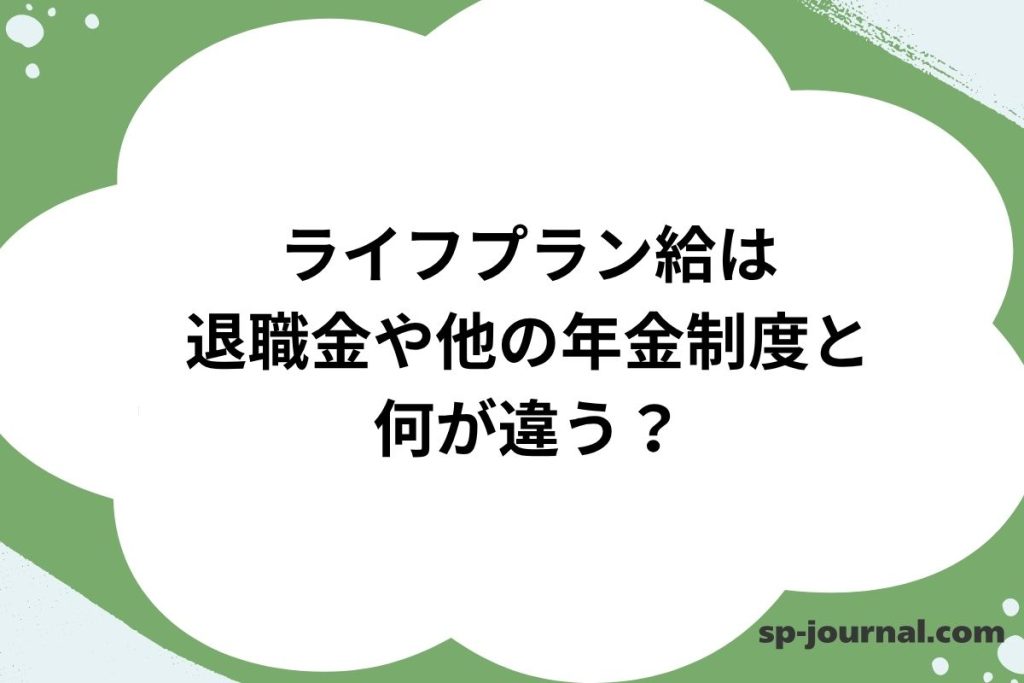
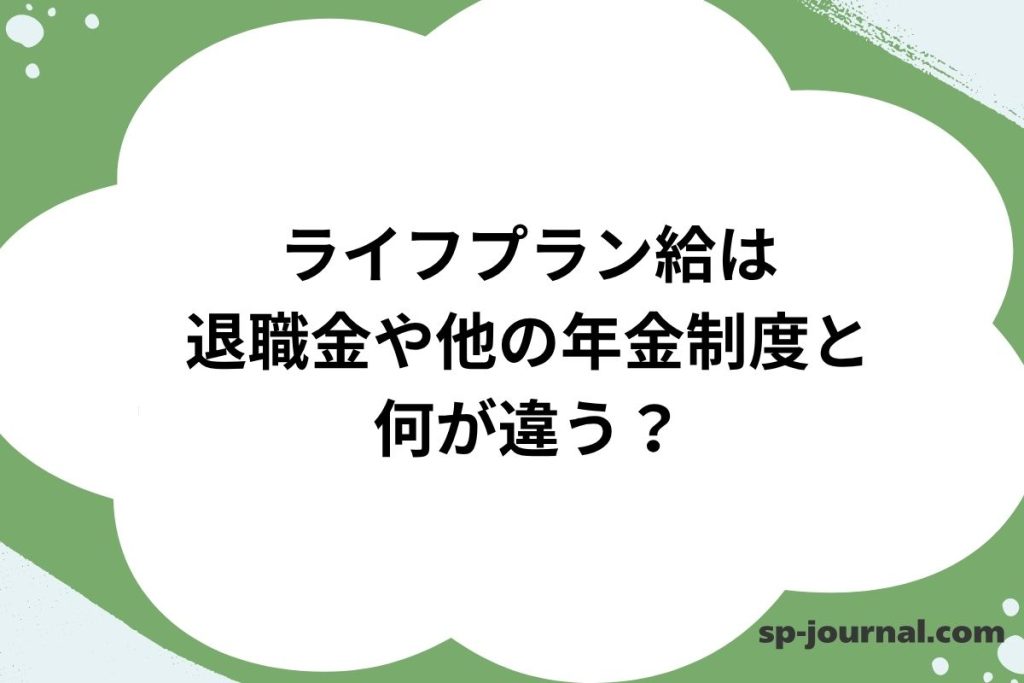
ライフプラン給は私的年金制度の中の1つです。ライフプラン給について、より理解を深めるためには、他の年金制度と何が違うのかを知っておく必要があります。



60歳でもらえるなら退職金と何が違うのかしら?



結果的に他の年金制度のほうが良かった、とならないですか?
退職金や年金制度を詳しく学ぶ機会は、通常それほど多くはありません。ですので、違いがわからず、他の年金制度のほうがよいかも、と考えてしまうこともあるでしょう。
このセクションでは、よく聞く、退職金・企業型確定拠出年金・個人型確定拠出年金の3つについて、それぞれの違いをわかりやすく説明していきます。ライフプラン給と何が違うのかをしっかり理解して、今後の運用に備えましょう。
退職金との違い
退職金は、退職時にまとめて受け取るお金です。通常、企業の規定に基づいて計算されるもので、一般的には勤続年数や基本給、企業の業績などから計算されます。
それに対し、退職金共済制度という制度に基づいて支払われるパターンもあります。この制度は、企業が毎月掛金を外部機関に積み立てていき、退職した際に外部機関から従業員に支払われます。これは中途退職した場合にも支払われるので、60歳未満でも受け取ることができます。
退職金も退職金共済制度も企業が積み立てるもので、従業員の給与から拠出することもありませんし、運用にも携わりません。
一方、ライフプラン給は在職中、給与から拠出され積み立てし、運用は従業員が担います。つまり、退職金が「企業が用意してくれる一時金」であるのに対し、ライフプラン給は「企業がサポートしながら自分で育てるお金」です。
拠出金額や運用の仕方を従業員自身がコントロールできるため、将来設計の自由度が高いというメリットがあります。
企業型確定拠出年金との違い
企業型確定拠出年金(企業型DC)には、企業拠出型、上乗せ型、選択制という3つのパターンがあります。ライフプラン給はそのなかの選択制といわれるもので、拠出金額を従業員が自由に決められる制度です。
それぞれの違いを比較してみましょう。
| 企業拠出型 | 上乗せ型(マッチング拠出) | 選択制(ライフプラン給) | |
| 制度の仕組み | 企業が掛金を全額拠出 | 企業拠出に加え、社員も自分の給与から上乗せ拠出できる | 社員が給与の一部を掛金として拠出するか、給与のまま受取るかを選択できる |
| 税制上のメリット | 拠出額は全額非課税(企業負担分) | 社員の上乗せ分も所得税・住民税が非課税 | 社員の拠出分が課税前控除され、社会保険料も軽減される |
| 社員の選択自由度 | なし(企業が一律設定) | 上乗せするかどうかを選べる | 拠出額を自分で決められ、現金受取も選べる |
| 社会保険料の負担 | 給与に影響なし(変化なし) | 給与総額が変わらないため影響なし | 拠出分が給与から除外されるため、社会保険料が減る |
| 給与明細上の見え方 | 拠出は見えない(企業負担) | 給与から天引き(上乗せ分のみ) | 拠出額・現金受取額を社員が把握しやすい |
| 将来資産形成の意識向上 | やや低い(受け身になりやすい) | 中程度(上乗せ意識あり) | 高い(自分で拠出を選び、老後資金意識が高まる) |
どのタイプも老後資金づくりが主な目的ですが、ライフプラン給は資産設計を自分自身で決めて築き上げていくタイプですので、他の2つより自由度が高く、積み立てた金額をしっかりと把握しておけるのが特徴です。
個人型確定拠出年金(iDeco)との違い
個人型確定拠出年金(iDeCo)は、個人が自分の意思で加入し、毎月掛金を拠出して運用する年金制度です。自由度の高さや、積み立てた金額が把握しやすいことはライフプラン給と似ていますが、すべて自分で煩雑な手続きを行わなければなりません。
それに対して、ライフプラン給は企業が従業員に支給する形で資産形成を支援するため、自分で手続きをする負担が少ないのがポイントです。



ライフプラン給は企業が将来の資金形成を促してくれる仕組みなんですね!



運用の自由度が高いから、運用益が大きくなることも期待できそうです。



その通りです!自由度が高いほうが、当然、高い運用益を得られる可能性があります。プライベートバンカーに相談すると、より安心できる運用方法をご案内できますよ!
個人型確定拠出年金(iDeCo)については、こちらにも資金形成の戦略記事があります。興味のある方はぜひお読みください。


あなたに合ったライフプラン給の選び方
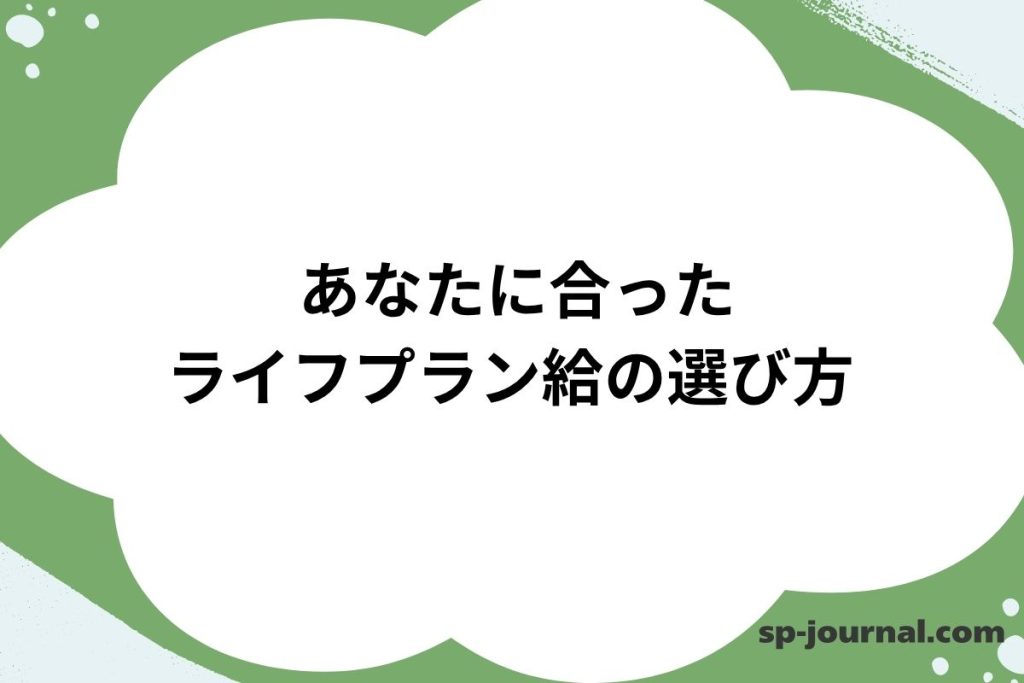
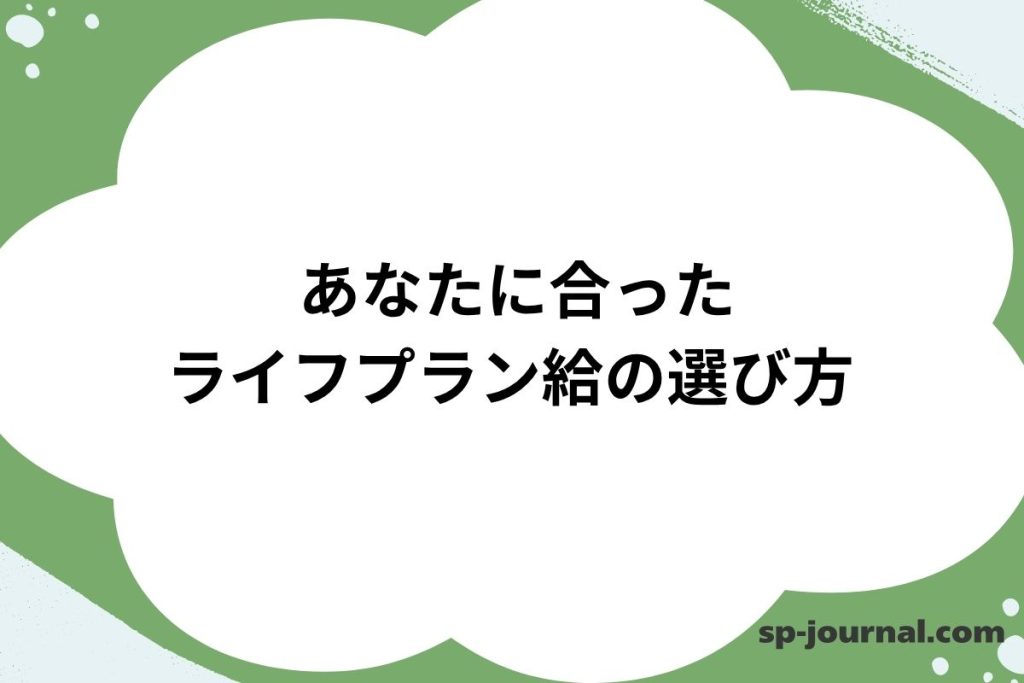
ライフプラン給は自由度が高いので、「最終的にどのくらいの金額まで積み立てるのか」「運用の仕方をどうするのか」を自分でカスタマイズすることができます。まずは自分のライフプランを考えてみるところから始めてみましょう。
あなたのライフプランを考える
ライフプラン給を上手に活用するには「自分の将来設計=ライフプランを明確にすること」が大切です。
例えば、次のような質問を自分にしてみましょう。
・5年後、10年後、または退職後、どんな生活を送りたいか?
・いつまで働く予定か?
・老後はどこに住むのか、どんな住まいがよいのか?
こうした問いに答えていくと、将来の生活にどれぐらいの金額が必要となるのか、が見えてきます。ライフプラン給は、将来の支出に備えて計画的にお金を積み立てるのにピッタリの制度です。
ライフプラン給の中には元本保証の「積み立て貯蓄型」と「資産運用型」とがあります。運用益と運用リスクのバランスを考えて選択できますし、2つとも選択することも可能です。
もし選択に迷ったり不安があるのでしたら、プライベートバンカーに相談してみましょう。



ライフプラン給の運用は、プライベートバンカーの腕の見せどころです!
他の年金制度と併用も
ライフプラン給は、個人型確定拠出年金(iDeCo)などと併用できる点も大きな魅力です。むしろ、老後の資産形成をしっかり行うには、複数の制度を組み合わせるほうが効果的といえます。
社会の変化とともに、働き方やお金の使い方も多様化しています。これからは「老後に備えつつ、人生を通じて自分のお金をデザインする」時代です。



あなたの企業がライフプラン給を導入しているなら、まずは仕組みを理解し、将来の安心のための第一歩を踏み出してみましょう!
他の年金制度のひとつに国民年金基金もありますよ。詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。


ライフプラン給を活用した資産形成の方法
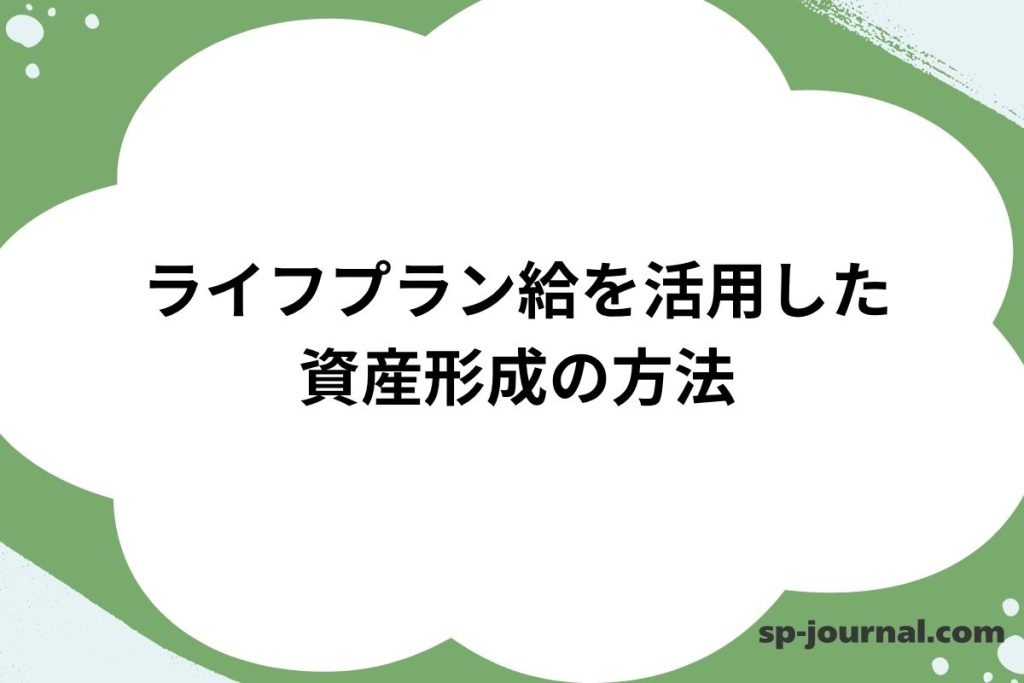
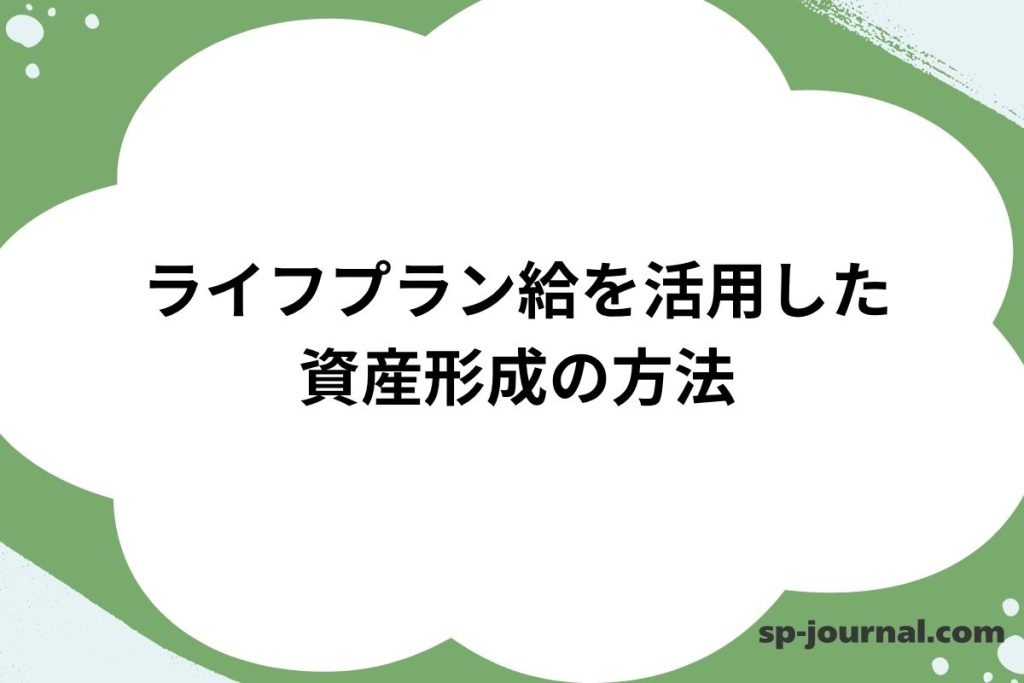
ライフプラン給を効果的に活用するためには、着実にステップを踏んで最終目的に到達することが重要です。
ここでは、ライフプラン給を活用して資産形成するための具体的な方法について説明します。適切な運用商品かつ複数の金融商品を選んで運用すれば、より効果的な資産形成が可能となるでしょう。
老後の安心に備えよう
老後の安心に備えるためには、ライフプランを明確にすることが重要である、と前のセクションで説明しました。やがて迎える退職とその先のセカンドライフは、安心で明るいものであってほしいと、誰もが考えるはずです。
従来の年金制度が老後の安心を与えてくれる時代は終わりかけています。自助努力で積み立てをした年金は確実に資産となり保護されるので、年金がもらえないかもしれない、という不安もありません。
あなたのライフプランに沿って、安心の老後のためのステップを一緒に考えていきましょう。
効果的な資産形成のステップ
ライフプラン給を使って資産を形成するための具体的なステップは3つあります。
《STEP 1》 時系列でライフイベントと資金を整理する
《STEP 2》 運用商品を選ぶ
《STEP 3》 運用開始後も必要に応じて運用プランを見直す
では、1つ目のステップです。時系列でライフイベントと資金を整理しましょう。
例えば、お子様の教育費、マイホーム購入など、まとまった資金が必要になるタイミングがあります。ライフプラン給を全額拠出してしまうと、イベントで必要となる資金を引き出すことができません。ですので、まとまった資金を使うタイミングや金額を考えて、拠出金額を決めていきます。



ライフプラン給として使える金額の中で、給与として受け取る分と、拠出して積み立てる分にわけることも考えるのですね。



その通りです!企業の規定などにもよりますが、ライフプラン給は自由度が高いので、数年後に金額を変更することもできるんです。
次はステップ2です。拠出する金額に対して、適切な運用商品を検討し、選択しましょう。



商品がたくさんありますし、運用リスクを考えると、どの商品を選んでいいのか、悩んでしまいます。



そんな時こそ、プライベートバンカーに相談してください!将来のプランに沿った最適な運用商品を一緒に考えましょう。
どんな運用商品が自分に合うのかわからないときは、ぜひプライベートバンカーに相談してみてください。経験豊富な専門家が、あなたのライフプランに合わせた商品をともに考え、提案してくれるはずです。
あるクライアントと一緒にライフプランと資金を整理した際には「初めて将来の必要資金を具体的に把握できました。」といいました。その後、資産運用の目標が明確になり、効果的な資産形成が進み、ライフプラン給のメリットを最大限に活用できたのです。
「自分の将来について、資金の道筋が明確になって、ぐっと安心感が増しました」と、後日、そのクライアントは話していました。
それではいよいよ、最後のステップです。
運用が開始されたら、必要に応じて運用プランを見直しましょう。社会情勢が変われば運用商品の利益率も変化します。頻繁にプラン変更はできませんが、年に1回は変更可能など、企業規定があるはずですので確認しておきましょう。
また、ライフプラン給では、他の年金制度と併用ができますので、個人型確定拠出年金(iDeCo)との併用なども検討してみるようにしましょう。どちらの制度も拠出分と運用益は非課税ですので、節税メリットを最大限に活かせます。



プライベートバンカーとして、クライアントに対しては、この『リスク分散と老後年金の増額を図る』アプローチを推奨しています。



実は、私自身もライフプラン給とiDeCoを併用していますよ!
SPJ公式LINEでは資産運用の有益な情報をお届けします!
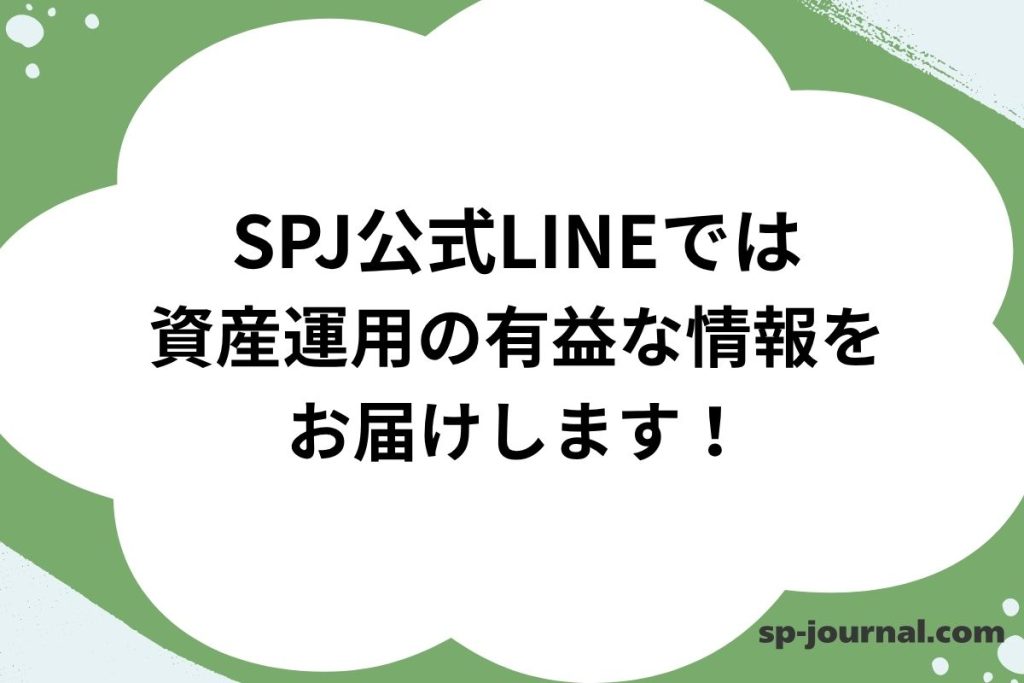
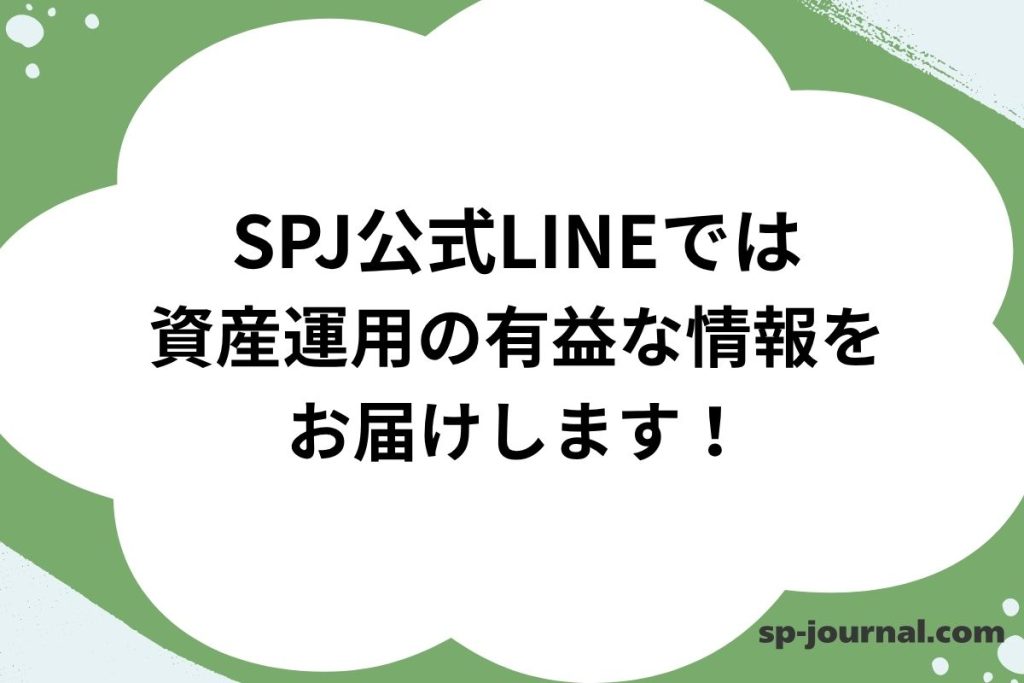
この記事では、ライフプラン給の基本概念から、その導入背景、給与やボーナスに与える影響、さらにはそのメリットとデメリットについて詳しく解説してきました。ライフプラン給を効果的に活用するには、順を追って資産形成のステップを踏むこと、最終的に他の金融商品、年金制度の併用を検討することも必要です。
この記事を通じて、ライフプラン給のメリットを理解し、将来の資産形成に役立てていただければ幸いです。老後を安心して迎えられる資産を築いていけるよう、長期的な目でライフプラン給を活用しましょう。



私のライフプラン給から実際にシミュレーションして、運用商品を選びたいです。



プロの目線で運用する方法を教えてもらえないでしょうか?
初めてライフプラン給について検討をする方は、こういった考えが必ずあるでしょう。
そこでSPJではSPJ公式LINEの登録をおすすめしています。あなたの資金形成について、一緒に考えていきましょう。また今なら、一部の富裕層にしか知られていない資産運用ノウハウに関する特別なセミナー動画も無料でプレゼント!
ぜひ、今すぐSPJ公式LINEを登録して、ライフプラン給を効果的かつ最大限に活用してください。安心で輝かしい未来をSPJとともに実現していきましょう!SPJ公式LINEで、あなたからの資産形成相談を心よりお待ちしています。